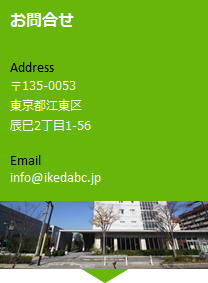事業再生コンサルタントの中小企業経営コラム
過去のスタグフレーションを知っておく~日銀百年史から
物価は上がる一方で景気が低迷するスタグフレーションになるかもといわれる現在の日本ですが、過去には実際にスタグフレーションに陥った時期がありました。
それは昭和49年、オイルショックのタイミングです。
その時、国、日銀はどう対応したのか、日本銀行百年史(https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/index.htm)に当時の流れが生々しく記録されています。
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ、といいます。
今回は、この日本銀行百年史を読みとき、過去のスタグフレーション発生時の経済動向を確認します。
これから日本に何が起き、どうなっていくのか、歴史から学んでみましょう。
スタグフレーションとの闘い
さて、この百年史におけるスタグフレーションの記載は、第6章変動相場制下の金融政策の、2. 減速経済下の金融政策にあります。2節ですね。
今回はこの2節の項たる(1) スタグフレーションとの闘い、と(2) 低圧経済下(昭和50年~53年)の金融緩和、を要約しつつ見ていきます。
ちなみにこの2つで37ページあります。
まずは「スタグフレーションとの闘い」から。
>深刻なスタグフレーションの経験-二けたインフレ下のマイナス成長-
石油ショックに伴う混乱が続くなかで幕をあけた昭和49年(1974年)のわが国経済は、二けたの物価上昇のもとでのマイナス成長という、特異な景気後退パターンを示した。
消費者物価も激しい騰勢を示し、49年中の年間上昇率(全国)は21.9%、年平均の上昇率は24.5%と敗戦後の混乱期以来の暴騰を示した。
昭和49年はまさにスタグフレーションの名にふさわしい事態に直面した年であった。
スタグフレーションの発生原因ですが、オイルショックと大幅賃上げにあると結論付けられています。実質総需要を大きく減退させた理由は、3つ。
①石油価格の大幅引上げ
②物価高騰に伴い消費者が買い急ぎから買い控えに転じた
③金融、財政の両面から総需要抑制政策が堅持された
です。プラス、かつてない大幅賃上げがスタグフレーション激化の大きな要因とされています。
賃上げ→製品価格への転嫁→物価上昇→総需要抑制→企業収益圧迫→投資活動停滞→景気後退深化
といった流れです。
大きな視点で見ると、景気過熱の反動という短期的側面と、高度成長期の終焉という長期的側面の両方、が影響したようですね。
では起きてしまったスタグフレーションについて、政府日銀はいったいどういった対応をしたのか、それを見ていきましょう。
>金融引締め政策の継続
本行は引締め継続方針を堅持した。
総需要の抑制を続けることにより現実の物価(とりわけ消費者物価)の騰勢を抑えるとともに根強く残存するインフレ心理を鎮静させ、これを通じて質金・物価の悪循環を断つことがねらい
不況のなかにあってもインフレーションの収束を基本としたのである。
49年7月の参議院選挙で自由民主党が予想外に大幅な後退を余儀なくされ、それは激しいインフレーションに対する国民の不満・不安の現われであるとの受け止め方が一般化するに及んで、政府、財界など広い範囲にわたって総需要抑制堅持のコンセンサスが形成されていった。
はい、利上げして物価上昇から止めに入ったのですね。
いつの時代も物価が上がると国民は騒ぐようです。そりゃデフレが長く続くはずです(結局失われた何十年とかになるわけですけど)
となればお金が回らなくなる、ということなので景気後退はどんどこ進んでいくわけです。もともと狙ってるんですからそりゃそうでしょう。大型倒産などもぼんぼこ出てきます。
となると物価下がるのはいいけどさすがに景気後退し過ぎー、という都合のよい話というか生活感のある意見が世を賑わすわけです。
低圧経済下(昭和50年~53年)の金融緩和
そこで政府日銀がとったのは金融緩和です。
いやはや上げたり下げたり大変です。
このくだりは(2) 低圧経済下(昭和50年~53年)の金融緩和、として記載があります。
>金融緩和へのタイミング
昭和50年に入り不況色が強まる気配のなかで、物価の騰勢も鈍化傾向がはっきりしてきた(卸売物価は年初来軟調に転じた)
本行は、こうした景気情勢や外部における政策転換要請に対し、慎重な姿勢を取り続けた。
本行は、卸売物価が年初来3月まで下落を続け、消費者物価の前年同月比上昇率が2月 (全国)、3月(東京)とも14前後にまで鈍化したことが明らかになり、他方春闘のベースアップ率が4月9日の鉄鋼回答(14.9%) を機に全体としてモダレートにとどまる公算が強まったことを確認してようやく公定歩合引下げの腹を固めるに至った。
その結果、4月15日、本行は公定歩合をそれまでの年9%(商業手形割引歩合) という高水準から0.5%引き下げ8.5%とすることを決定し、翌16日から実施した
4月の公定歩合引下げ後本行は6月、8月と2か月おきに連続して公定歩合を0.5%ずつ引き下げた。
慎重な緩和テンポを堅持することによって、高度成長時代にみられたような景気急回復へのイリュージョンを企業に抱かせぬよう留意し、インフレ心理の払しょくを徹底させることが何よりも重要と考えたからであった。
物価高騰に懲りたのか景気が後退してもまだ物価上昇を気にして景気をどんどん悪化させていきます。
>不況の長期化と本格緩和への転換
消費者物価も騰勢が鈍化し、前年同月比上昇率は逐次低下して8月には10%にまで下落した。
企業の潜在的値上げ意欲は依然根強いとはいえ、物価の落着き傾向はかなり定着してきたと判断されるに至った。
株式会社興人の「会社更正法」適用申請という、いわゆる大口倒産が発生
諸情勢のなかで本行は9月半ばに至り、8月の公定歩合引下げ後約1か月しか経過していなかったが、公定歩合を1%引き下げ、本格的な金融緩和の意思表示をする意向を固めた。
物価抑制のために景気を下げたのが、完全に不況入りするまで薬が効いてしまいました。
なんかバブル崩壊時の総量規制に通じるものがありますね。
>昭和50年11月と51年1月の準備預金準備率引下げ
量的な金融調節手段についても緩和措置をとろうとした
昭和50年のわが国経済は前述のように後半に景気の回復テンポが鈍化したものの、同年の実質国民総支出は前年比2.4%増と前年のマイナス成長から脱出
一方物価は卸売物価が年間上昇率1.1%、年平均上昇率3.0%と落着きを示し、消費者物価も年平均上昇率は11.8%となお二けた台を示したものの、年間上昇率は7.6%と一けたに縮まってしだいに落着きの方向を示し、前年のスタグフレーションから相当の改善を示した。
物価上昇はなかなか止まらないものの、金利を下げても景気が戻らないので、量的緩和に踏み切りました。アベノミクスの始まりも似たようなことありましたね。量的緩和は刺激策としてかなり効くようです。
>赤字国債の発行と昭和51年前半の一時的景気回復
本行は、景気は回復過程をたどっており、一方企業金融面での緩和はすでに十分浸透し、着実な景気回復に必要な企業流動性は確保されているとの判断に立って、金融政策運営方針をそれまでの緩和促進から、締めもせず緩めもしない、いわば景気に中立的な姿勢に切り替えた。
しかし、51年後半に入ると、景気回復への動きはしだいに弱まった。
量的緩和は十分かなと思ってちょっと閉めたらすぐに景気が下り坂に。
まさにカンフル剤というか刺激がないとダメな感じの状況です。
今回も物価上昇やばいといって利上げしたら景気が冷え込み過ぎて戻らん、みたいな「いつか来た道」を辿りそうな気がしてなりません。。
>昭和52年3月、4月の連続公定歩合引下げ
民間最終需要は依然伸び悩みを続け、企業の先行き景況観には明るさがうかがわれない状態が持続
本行は総じて弱気に傾いている企業家心理に多少とも明るさを取り戻させるため、条件さえ整えば比較的大幅な公定歩合引下げを行うのが適当との判断を固めた
ぜんぜん景気が戻らないので利下げです。
いったん落ちるとなかなか帰ってこないんですね。
なんとも手綱さばきが難しい。
>国際収支黒字をめぐる海外の対日批判と昭和52年秋の公定歩合引下げ
内外の諸情勢、ならびに卸売物価は春以降弱含みに推移し、マネー・サプライ (M2平均残高)の前年比伸び率は3月以降11%台へとさらに低下していることなどを併せ考慮し、第7次の公定歩合引下げを決意するに至った。
経済環境を強くするためにまた利下げ。
オイルショックからの回復に全世界が悩むなか、景気の先導役として日本の役割が注目されている中で、景気刺激策をとらないわけにはいかない的な展開に。
>昭和52年秋からの急速な円高と積極財政の展開
石油危機に伴うトリレンマという直接的ショックは、51年中にほぼ解消したといえる。
52年は、こうした事態の改善に伴い企業や個人のコンフィデンスが回復し、景気が本格的回復に向かうことが期待されたが、既述のように民間最終需要が依然伸び悩み、景気が軽微な後退過程に入っているなかで、さらに為替相場が変動相場制移行後初めての大幅かつ急速な円高現象を示し、これによって企業マインドは攪乱的影響を被り、経済の調整過程は一段と長期化した。
昭和51年以降円相場が上昇するなかで、とくに52年秋以降の急激かつ大幅な円高の動きは、変動相場制下ではどこまで円高が進展するか不明なだけに企業の戸惑いと先行き警戒感を強めることになった。
景気の戻りがなかなか見えないタイミングで、悪いことに円高が進行。景気を支えてきた輸出企業が凹み始めました。
今回は円安からの輸入コスト増加という景気悪化要因を、輸出企業のプラスによって跳ね返している感じでしょうか。というと内需系は厳しいですね。
>昭和53年3月の公定歩合引下げと景気情勢の好転
積極財政方針はビジネス・マインドにやや明るさを与え、また実需面でも2次にわたる公共事業追加措置の影響は52年末から翌53年初めにかけて建設関連品目の市況好転という形で現われてきたが、このような財政面からの景気刺激効果を考慮しても、政府の53年度経済見通しに掲げられた7%成長のような経済情勢の好転が生ずるという見方は当時世上ではほとんど見受けられなかった
国際収支大幅黒字のなかで円高がどこまで進むか見極めがたく、その度合いいかんによっては経済動向に及ぼす影響が定かでないこと、
また当時大企業について4社に1社が赤字という企業間格差の大きい企業収益状況からみて、企業体質の累積的悪化に伴う倒産、失業の増大が避けがたいのではないかとみられること、などの諸点にとくに留意しなければならぬと考えていた。
3月に入り為替相場の円高傾向が急進展するなかで同月上旬本行は公定歩合の早期引下げ (引下げ幅0.75%)、預貯金金利同幅引下げの考えを固めた。
円高がさらに進行したことで、更なる利下げを実施。
こうなってくると当初重視していた物価高騰よりも不況脱出が重点項目になったようです。
また、為替が大きなキーになっている感じですね。
以上が(1) スタグフレーションとの闘い、と(2) 低圧経済下(昭和50年~53年)の金融緩和の要約と感想となります。
全体通して、量的緩和が劇薬であることはわかりました。
この開け閉めで景気が相当上下するようです。
量的緩和、という言葉が新聞紙上をにぎわすようになったら、これから景気が大きく変わっていくんだな、と考えてよさそうですね。
とりあえず、一旦スタグフレーションに陥ると、物価上昇か景気後退かどちらかを優先して解決していく癖は政府日銀にはあるようです。
そういう視点で見ると日々の金利動向や日銀の動きも自分事として注目できるトピックですね。
中小企業経営者の悩みに寄り添った事業再生・再成長支援
池田ビジネスコンサルティング
前の記事◀取締役の責任と損害賠償
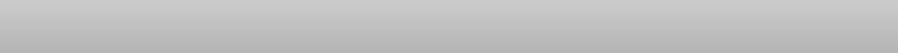
 事業再生支援、資金繰り改善、補助金申請サポートなど、中小企業の経営課題を解決します。
事業再生支援、資金繰り改善、補助金申請サポートなど、中小企業の経営課題を解決します。